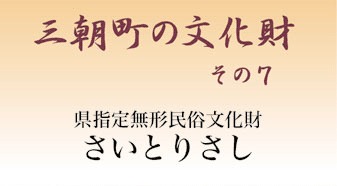 |
 |
「さいとりさし」は漢字で「刺鳥刺」と書き、殿様が鷹狩に使う鷹の餌として小鳥を捕ることを意味し、またそれを仕事とする人の職名でもあります。 さいとりさし踊りは、天下御免の鑑札を持つさいとりさしが権力を笠に着ることに反発した民衆が、さいとりさしの鳥を捕る様子を身振り手振りで狂言風に踊ったのが始まりと伝えられています。 やがて、鳥を捕ることから転じて、「嫁をとる」、「福をとる」などとして、祝狂言として伝承されてきました。三朝町のさいとりさしは関金町のさいとりさしとともに昭和四十九年に鳥取県から無形民俗文化財の指定を受けました。 さいとりさし踊りを伝承する三朝町さいとりさし踊り保存会は、昭和三十二年の結成以来県内外の多くのイベントに出演し、さいとりさしや三朝温泉の周知に尽力してきました。 また、町内の小学生への指導など、後世へ伝承するための活動も精力的に行っています。 平成十六年には、その功績が認められ、文部科学大臣表彰を受けました。 |
|
おわりに 六月の天気具合では、今年は空梅雨かと思えば、豈図らんや、七月に入っての集中豪雨は晴天の霹靂ならぬ、雨天の辟易であった。「過ぎたるは及ばざるが如し」や「帯に短し、襷に長し」だと何もしないほうがかえって良かったと言われても致し方ない。何事も適当が肝要。 |
|